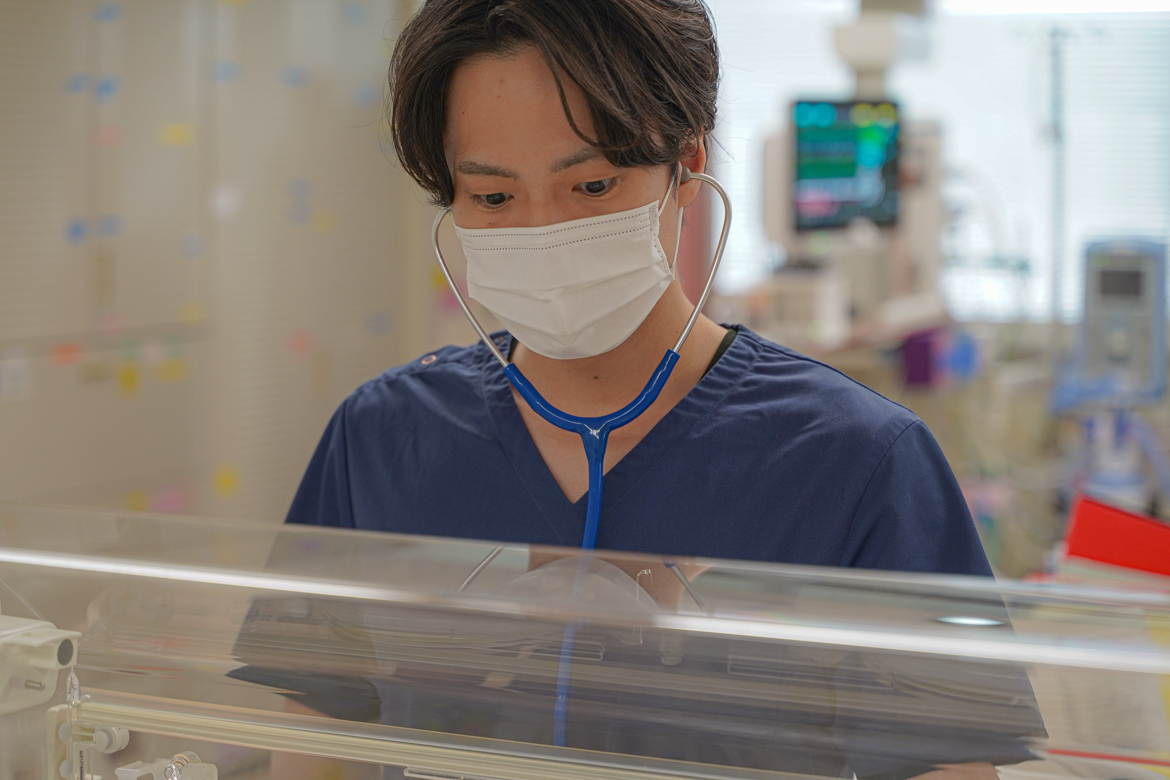「授乳後にゲップさせようとしているけど、なかなか出てくれない…」「ゲップがうまくできないと、赤ちゃんに負担があるのでは?」と心配されているママやパパは多いのではないでしょうか。特に新米ママパパにとって、赤ちゃんのゲップは毎日の授乳ケアで悩みのタネになりがちです。
この記事では、赤ちゃんのゲップがうまくできない原因や、効果的なゲップの出し方について解説します。さらに、「ゲップが出ないときはどうすればいいの?」という疑問にも、実践的なアドバイスを交えてお答えします。
赤ちゃんのゲップはなぜ必要なの?
まず、なぜ赤ちゃんにゲップが必要なのか、その基本的な理由と影響を理解しておきましょう。
授乳中に飲み込む空気の問題
赤ちゃんは母乳やミルクを飲む際に、同時に空気も飲み込んでしまいます。これは避けられないことで、特に新生児期には顕著です。この飲み込んだ空気が胃の中に溜まると、不快感やお腹の張りを引き起こします。
授乳中の赤ちゃんを観察していると、おっぱいや乳首の加え方が十分でなかったり、時々飲むのを中断して呼吸する様子が見られますが、このタイミングでも空気を飲み込みやすくなっています。また、泣いていた赤ちゃんが急に授乳を始める際も、大量の空気を一緒に飲み込むことがあります。
ゲップが出ないときの悪影響
飲み込んだ空気が胃に溜まったままだと、赤ちゃんにとって様々な不快症状を引き起こす可能性がいくつかあります。
- お腹の張りによる不快感
- ぐずりや泣きの原因になる
- 吐き戻しが増える可能性
- 消化不良の原因になることも
- 睡眠の質に影響することがある
こうした理由から、授乳後に適切なタイミングでゲップを促すことは、赤ちゃんの快適な消化と健やかな成長をサポートする重要なケアの一つです。
赤ちゃんによっては、飲み込んだ空気が原因で不快感などから体を反り返らせるような動きを見せることもあります。実はこの「反り返り」も、ゲップと関係していることがあるのです。反り返りが見られる場合には、ゲップ以外の原因も考慮する必要があります。詳しくは、以下の記事をご覧ください。
赤ちゃんの反り返りはなぜ起こる?原因と対処法を解説 | Sodate(ソダテ)
赤ちゃんのゲップがうまくできない主な原因
ゲップがなかなか出ない理由には、いくつかの要因が考えられます。効果的な対策を行うために、まずはその原因を理解しましょう。
授乳方法と空気の飲み込み
赤ちゃんがゲップをうまくできない原因の一つとしては、授乳方法が適切でないために空気飲みが多くなっていることが考えられます。
母乳育児の場合、赤ちゃんが乳首に正しく吸い付けていないと、授乳中に余計な空気を飲み込みやすくなります。また、ミルク育児では哺乳瓶の角度が不適切だったり、乳首の穴が大きすぎたり小さすぎたりすると、赤ちゃんは空気を多く飲み込むことになります。たくさん飲み込んだ空気は、後述する胃軸捻転と関係することで胃を圧迫し、かえって空気が出づらい状況を作る原因となります。
特に注意したいのは、哺乳瓶のミルクが完全に乳首部分まで満たされていない状態での授乳です。この場合、赤ちゃんは空気も一緒に吸い込んでしまいます。
赤ちゃんの消化器官の未熟さ
新生児期の赤ちゃんは、消化器官がまだ十分に発達していません。新生児期の赤ちゃんの胃は「胃軸捻転症」のためゲップが出づらいという特徴があります。。
生まれたばかりの赤ちゃんの胃は、お腹の中での固定性が未熟であるため「胃軸捻転症」という状態になる傾向があります。これは哺乳後などに胃が圧迫されることで、哺乳時に一緒に飲み込んだ空気が胃の入り口側に移動しにくい構造になり、なかなかゲップとして空気が抜けないという状況が起こり得ます。このため空気はゲップではなく小腸の方に流れるようになり、お腹のハリの増強などにつながります。ゲップを出そうとして一緒にミルクを吐き戻してしまったりすることもあります。
この未熟さは、月齢が上がるにつれて徐々に改善されていきます。そのため、新生児期はゲップが出にくいですが、成長するにつれて少しずつ自分で上手にゲップを出せるようになっていきます。
ゲップを促す姿勢・体勢の問題
赤ちゃんのゲップを促す際の抱き方や姿勢も、ゲップがうまく出るかどうかに大きく影響します。
例えば、赤ちゃんの背中や首が曲がっていたり、体全体が安定していなかったりすると、空気が胃から食道を通って口まで上がってくるのが難しくなります。特に首がすわっていない新生児期は、適切なサポートが必要です。
また、ゲップを促す時間が短すぎたり、赤ちゃんがすでに眠ってしまっている状態だと、ゲップが出にくくなることもあります。
個人差と体質による影響
全ての赤ちゃんが同じようにゲップをするわけではありません。赤ちゃんによって、空気を飲み込む量や胃の形状、消化器官の発達速度には差があります。
中には、授乳中にほとんど空気を飲み込まず、そもそもゲップ自体があまり必要ない赤ちゃんもいます。また、ゲップの出し方にも個人差があり、一度で簡単に出る子もいれば、時間をかけて少しずつ出す子もいます。
赤ちゃんが毎回完璧にゲップをする必要はありません。そのことを知っておくことも、育児中の安心につながります。
育児には個人差があるように、成長や発達のスピードにも個人差があります。赤ちゃんの月齢ごとの成長や発達の目安を知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
【小児科医監修】月例別!赤ちゃんの成長と発達 ? 0歳から1歳までの変化 | Sodate(ソダテ)
効果的なゲップの出し方と実践テクニック
ゲップがうまく出ない時の解決策として、効果的なテクニックをいくつかご紹介します。赤ちゃんの様子を見ながら、お子さんに合った方法を見つけてみてください。
肩に赤ちゃんの顎を乗せる縦抱きの方法
最も一般的で効果的なゲップの出し方が、縦抱きで赤ちゃんの顎をママやパパの肩に乗せる方法です。
まず、赤ちゃんを縦に抱き、顎をママまたはパパの肩の上に優しく乗せます。この時、赤ちゃんの背中全体が真っ直ぐになるよう意識してください。片手で赤ちゃんの首と背中をしっかり支え、もう一方の手で背中全体を優しくトントンと叩いたり、下から上へ向かって円を描くようにさすったりします。
手はカップ状(少し丸めた形)にすると、より効果的にゲップを促せます。力加減は「軽め」が基本で、赤ちゃんが不快にならない程度を心がけましょう。このとき、吐き戻しに備えて肩にタオルやガーゼを掛けておくと安心です。特に新生児期は吐き戻しが多いため、準備しておくと良いでしょう。
膝座らせスタイルでのゲップの促し方
縦抱き以外にも効果的な方法として、膝座らせスタイルがあります。
ママまたはパパのお膝(太腿)の上に赤ちゃんのお尻〜腰部分を座らせ、赤ちゃんの体を少し前傾させます。この時、背筋から首筋まで真っ直ぐになるよう意識しながら、片手で赤ちゃんの顎を支え、もう一方の手で背中を優しくトントンと叩いたり、さすったりします。この姿勢は赤ちゃんの腹部が少し圧迫されるため、ゲップが出やすくなる場合があります。
首のすわっていない新生児には必ず頭と首をしっかり支える必要があります。両脇をしっかり支えて安定させることがポイントです。
うつ伏せスタイルでのゲップ促進法
もう一つの効果的な方法が、うつ伏せスタイルです。ママまたはパパの太腿や腕の上で、赤ちゃんのお腹側を下向きにして寝かせます。顔は横向きにして呼吸が妨げられないよう注意しましょう。その状態で背中全体、特にお尻寄りから頭方向へ向けて優しく叩いたり、さすったりします。
この姿勢は重力の助けもあってゲップが出やすくなることがありますが、赤ちゃんの顔周辺には十分注意が必要です。また、首がすわっていない赤ちゃんの場合は、頭と首をしっかり支えることが重要です。
下記は、赤ちゃんの抱き方と月齢に関する表で、各抱き方のポイントをまとめています。お子さんそれぞれのげっぷの出やすい方法を見つけてあげられると役に立つと思います。一つの方法にこだわらず色々な体位を試すことも有効です。
| 抱き方 | 適した月齢 | ポイント |
|---|---|---|
| 縦抱き | 新生児〜 | 背筋と首筋を真っ直ぐに/肩にもたれさせる/力加減は軽めに |
| 膝座らせ | 首すわり頃〜 | 太腿に座らせる/体を軽く前傾/両脇をサポート |
| うつ伏せ | 全月齢(要注意) | 太腿や腕の上に/顔は横向きで安全確保/背中を優しくトントン |
より効果的なゲップのためのコツとタイミング
ゲップを促す基本的な姿勢を理解したら、さらに効果を高めるためのコツやタイミングについても知っておくと役立ちます。
授乳前後の工夫とポイント
ゲップの出やすさは、授乳方法自体にも大きく影響されます。効果的な授乳方法を心がけることで、赤ちゃんの空気の飲み込みを減らし、ゲップの問題を予防できます。
母乳育児の場合は、赤ちゃんが乳首に深く吸い付けるよう意識しましょう。浅い吸い付きは空気を多く飲み込む原因になります。また、ミルク育児では哺乳瓶を傾け、乳首部分に常にミルクが満たされているようにします。
特にミルクの場合、授乳中も1〜2回ゲップのためにいったん中断すると、胃に空気が溜まりすぎるのを防げます。これは多くのミルクを一度に飲む赤ちゃんに特に効果的です。また、授乳前に赤ちゃんが激しく泣いている場合は、まず落ち着かせてから授乳を始めると、空気の飲み込みを減らせます。
ゲップを促すベストタイミング
ゲップを促すタイミングも重要です。一般的に授乳直後が最も効果的ですが、その他にも押さえておきたいポイントがあります。
授乳後はなるべく早めにゲップを促すと効果的です。授乳終了後すぐに横にしてしまうと、溜まった空気と一緒に吐き戻しを引き起こすことがあります。特に授乳中に赤ちゃんが頻繁に中断したり、飲み方が急いでいたりする場合は、空気を飲み込んでいる可能性が高いので、丁寧にゲップを促しましょう。
また、夜間授乳の際もゲップは重要です。「寝ているから起こしたくない」と思うかもしれませんが、ゲップをせずに寝かせると、入眠中に吐き戻しが多くなったり、後で不快感で目覚めることがあります。優しく促すことで、より安定した睡眠につながることが多いです。
試してもゲップが出ない場合の対処法
いくつか方法を試しても、どうしてもゲップが出ない場合があります。そんなときの対処法も知っておきましょう。
まず、一つの姿勢で2〜5分程度試してみて、それでも出ない場合は無理に続ける必要はありません。姿勢を変えて別の方法を試したり、少し時間を置いてから再度挑戦したりするのも効果的です。
赤ちゃんが機嫌よく、苦しそうな様子がなければ、無理にゲップを出す必要はないこともあります。多くの場合、飲み込んだ空気は時間が経つとオナラとして下から排出されることもあります。
また、ゲップの音が出なくても、小さな「ふー」という息のような形で空気が出ていることもあるので、必ずしも大きな音が必要というわけではありません。
月齢による変化とゲップの必要性
赤ちゃんの成長に伴い、ゲップのパターンや必要性も変化していきます。月齢ごとの特徴を理解しておくと、適切なケアができるようになります。
新生児期のゲップの特徴と注意点
生後1ヶ月までの新生児期は、消化器官が最も未熟な時期です。この時期は特にゲップのケアが重要になります。
新生児は授乳中に比較的多くの空気を飲み込みやすく、また消化器官の未熟さからゲップが出づらいため、丁寧なゲップのサポートが必要です。首がまだすわっていないので、抱き方にも注意しましょう。
この時期は吐き戻しも多いため、ゲップの後もしばらく縦抱きを続けるか、少し頭を高めにして寝かせると良いでしょう。授乳後30分程度は横にならないようにすると、吐き戻しのリスクを減らせます。
3〜6ヶ月頃の変化とセルフねんね時の対応
首がすわり始める3ヶ月頃から、赤ちゃんの消化器官も少しずつ発達し、ゲップのパターンにも変化が見られるようになります。
この頃になると、自分でゲップができるようになる赤ちゃんもいます。また、授乳中に空気を飲み込む量も減ってくるため、毎回の授乳後に必ずゲップが必要というわけではなくなってきます。
特に注目したいのが「セルフねんね」(自分で寝る練習)を始める時期との関係です。就寝前の授乳でゲップをさせると赤ちゃんが目を覚ましてしまうケースもあるため、赤ちゃんの様子を見ながら柔軟に対応するのがポイントです。
ただし、明らかに不快感がある場合や、寝かせた後にすぐに泣き出す場合は、ゲップが必要なサインかもしれません。
離乳食開始後のゲップと消化の関係
離乳食が始まる生後5〜6ヶ月頃になると、消化器官がさらに発達し、ゲップの必要性や様子も変わってきます。
この時期になると、多くの赤ちゃんは授乳中の空気の飲み込みがかなり減り、ゲップの必要性も相対的に低くなります。また、自分でゲップができるようになる子も増えてきます。
離乳食開始後は、むしろ食べ物の消化に関する新たな課題が出てくることがあります。例えば、新しい食材による便秘や消化不良などです。この時期は、ゲップだけでなく全体的な消化の様子に注意を払うことが大切です。
離乳食と母乳・ミルクのバランスを取りながら、赤ちゃんの消化の様子を観察することで、個々の赤ちゃんに合ったケアができるようになります。
生後5〜6ヶ月の離乳食の始め方や進め方、初期レシピの例について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
離乳食初期(5〜6ヶ月)・ゴックン期の進め方やレシピを紹介! | Sodate(ソダテ)
まとめ
赤ちゃんのゲップは、新米ママパパにとって意外と悩みの種になることがありますが、この記事で紹介した知識と方法を参考にすれば、より効果的にサポートできるようになるでしょう。
赤ちゃんのこうした成長のひとつひとつを見守る毎日が、子育てのやりがいであり、同時に忙しさでもあります。そんな子育て期の暮らしをもっと快適にするためには、住まいの工夫も大切です。アイフルホームでは、赤ちゃんや子どもの成長に寄り添った「キッズデザイン」の視点から、安全で片付けやすく、育児がしやすい住まいをご提案しています。毎日の育児がもっとスムーズに、家族みんなが笑顔になれる住まいづくりを考えてみませんか?