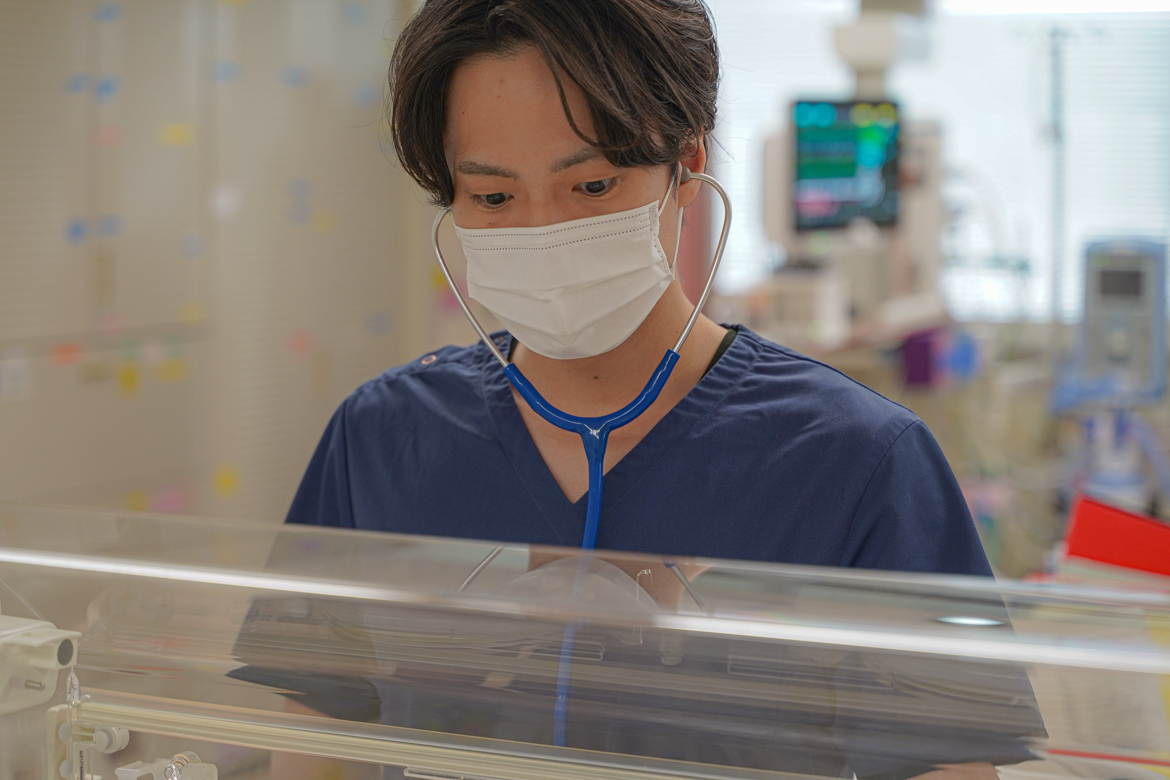赤ちゃんがなかなかうんちをしない、うんちが出ても固くて苦しそう…。そんな様子に不安を感じている親御さんも多いでしょう。実は、赤ちゃんの便秘は珍しくなく、多くの家庭が直面する悩みです。
この記事では、育児の専門家や小児科医が推奨する「赤ちゃんの便秘解消法」を3つのポイントに絞ってご紹介します。これらの対策を日常に取り入れることで、赤ちゃんのお腹の不調を和らげ、親子ともに快適な毎日を送るお手伝いをします。
赤ちゃんの便秘とは?判断基準とその原因
まず、赤ちゃんの便秘を正しく理解するために、判断の基準と原因について確認しておきましょう。
赤ちゃんの便秘の特徴と判断基準
赤ちゃんの便秘は、単純に「何日間排便がない」という日数だけでは判断できません。以下のような状態が見られる場合、便秘の可能性があります。
- 排便時に顔を真っ赤にして泣く、苦しそうにする
- 便が硬く、コロコロとした状態になっている
- 排便回数が極端に減った
- お腹が張って硬くなっている
哺乳後に吐き戻しが多い
特に注意したいのは赤ちゃんの様子です。排便間隔が空いていても、機嫌が良く、便が柔らかければ心配は少ないでしょう。一方、排便時に痛がったり、便が硬い場合や、哺乳量が減っている場合は便秘対策が必要です。
年齢や栄養によって変わる赤ちゃんの便秘の傾向
赤ちゃんの便秘は、月齢や授乳の方法(母乳・ミルク)や、離乳食の進み具合によって変わってきます。新生児期の赤ちゃんは、授乳のたびに排便が見られるなど便の回数が多いのが特徴です。出生後から数ヶ月にかけては、腸の発達に伴い、成長と共に排便回数が減少していくのが普通です。
母乳で育てている赤ちゃんは消化が良いため、そもそもの便量が少なく、排便間隔が開くことがあります。一方、粉ミルクの場合は、母乳に比べて便がやや硬い傾向があります。授乳量の不足は便秘を進める原因になるため、十分な量の哺乳をさせることが重要です。
生後数ヶ月になると、1日1回、もしくは数日に1回程度まで排便間隔が空くようになります。さらに、離乳食が始まる生後5ヶ月以降からは、食事の形態が徐々に食べ物へと変わることで便が硬くなり、便秘の症状が顕著になることがあります。
離乳食が始まると、食物繊維の摂取や水分バランスの変化から便秘になりやすくなります。そのため、離乳食の食材選びや水分補給がとても大切です。
よくある便秘の原因
赤ちゃんが便秘になる主な原因には、以下のようなものがあります。
- 水分不足(特に離乳食開始後や暑い季節)
- 腸の未発達による消化機能の未熟さ
- 食物繊維の不足(離乳食期)
- 母乳からミルク、離乳食への移行による腸内環境の変化
- 運動不足(特にハイハイや歩き始める前の赤ちゃん)
これらの原因を理解した上で、次に紹介する具体的な解消法を試してみましょう。
赤ちゃんの便秘解消法① お腹や肛門周りのマッサージ・運動
特に生後間もない赤ちゃんの便秘解消に最も手軽で効果的な方法が、お腹のマッサージと適度な運動です。どちらも薬に頼らず自然に腸の動きを促す方法として、推奨されています。
効果的なお腹のマッサージ方法
お腹のマッサージは腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を促し、便の排出をサポートします。以下の手順で行いましょう。
1. 赤ちゃんをリラックスさせた状態で仰向けに寝かせる
2. 手のひら全体を使って、おへそを中心に時計回りに優しく円を描くようにマッサージする(腸の流れと同じ方向)
3. 力を入れすぎず、1回につき5〜10分程度行う
4. 朝晩2回など、定期的に続けることが効果的
マッサージは、授乳後30分程度経過した時間や、オムツ替えのときなど、赤ちゃんが機嫌の良い時間帯に行うとスムーズです。入浴後の温まった体に行うと、さらに効果が高まります。
赤ちゃんとのスキンシップを通じて便秘を予防したい方には、ベビーマッサージもおすすめです。心地よい刺激で赤ちゃんのリラックスにもつながります。
ベビーマッサージのやり方と効果とは?赤ちゃんと一緒にリラックス! | Sodate(ソダテ)
便秘解消に効果的な赤ちゃんの運動
体を動かすことも腸の動きを活発にし、便秘解消に役立ちます。下記の運動を参考にして、ぜひ取り入れてみましょう。
- 足の自転車こぎ運動:赤ちゃんの両足を持ち、自転車をこぐような動きをさせる
- 膝曲げ伸ばし:両足を揃えて膝を曲げ、お腹に近づけたり離したりする
- 腰ひねり体操:両足と肩を軽く持ち、ゆっくりと上半身と下半身を反対方向にひねる
これらの運動は、オムツ替えの時や機嫌の良い時に遊び感覚で取り入れるとよいでしょう。赤ちゃんが笑顔になるような声かけをしながら行うことで、楽しい時間にもなります。
首や体の動きが安定してくると、運動のバリエーションも広がります。月齢ごとの発達の目安も合わせて確認しておくと安心です。
首すわりはどういう状態でいつから?遅い子の原因や練習方法と注意点 | Sodate(ソダテ)
綿棒浣腸による刺激法
マッサージや運動で改善しない場合、「綿棒浣腸」と呼ばれる方法も効果的です。これは肛門に軽い刺激を与えることで排便反射を促す方法です。
1. 清潔な綿棒にベビーオイルや白色ワセリンを薄く塗る
2. 赤ちゃんを仰向けに寝かせ、両足を軽く持ち上げる
3. 綿棒を肛門から1〜2cm程度の深さまで優しく挿入し、円を描くように軽く刺激する
4. 10〜15秒程度の刺激する
この方法は即効性がありますが、力を入れすぎないよう注意し、清潔な状態で行うことが大切です。日々の排便ケアの方法として行っても問題ないですが、実施することに抵抗がある場合には、数日排便がなく苦しそうな時の対応として考えましょう。
赤ちゃんの便秘解消法② 食事内容と水分補給の見直し
赤ちゃんの便秘は食事内容や水分摂取量に大きく影響されます。特に離乳食が始まってからは、食材選びや水分補給の工夫が便秘対策の鍵となります。
母乳・ミルク育児中の赤ちゃんの便秘対策
完全母乳やミルク育児の赤ちゃんでも便秘は起こります。
ミルク育児の場合は、ミルクの濃度が適切か確認しましょう。規定量より濃いミルクは便秘の原因になることがあります。
どちらの場合も、授乳と授乳の間に白湯を少量与えることで水分補給を促すことは便秘予防につながります。
離乳食期の便秘に効く食材選び
離乳食が始まると食材選びが便秘対策に大きく影響します。以下の食材は特に便秘解消に効果的です。
- 食物繊維が豊富な野菜:かぼちゃ、さつまいも、ほうれん草など
- 果物:りんご、バナナ(熟したもの)、梨など
- 発酵食品:ヨーグルト、手作り甘酒(アルコールなし)など
- オリゴ糖を含む食品:玉ねぎ、バナナなど
これらの食材をバランスよく取り入れましょう。例えば、「かぼちゃとヨーグルトのペースト」や「バナナとりんごのスムージー」などは離乳食として取り入れやすく、便秘解消効果も期待できます。
ただし、食物繊維を急に増やしすぎると逆にお腹を壊す原因になるため、少しずつ量を増やしていくことが大切です。
離乳食期は食材選びとあわせて、調理方法の工夫も便秘予防に効果的です。やわらかく甘みのある野菜から始めるのもおすすめです。
離乳食のかぼちゃレシピ|初期・中期・後期のおすすめ調理法と注意点を解説 | Sodate(ソダテ)
水分補給の重要性と適切な量
赤ちゃんの便秘解消には、水分補給が非常に重要です。特に離乳食が始まると、固形物の摂取量が増える分、水分が不足しやすくなるので注意が必要です。
離乳食期の水分補給のポイントは以下のとおりです。
1. 白湯や麦茶などを離乳食の合間に少量ずつ与える
2. 暑い季節は特に水分補給の回数を増やす
3. スープやとろみのある料理で水分を摂取させる工夫をする
4. 母乳・ミルクも重要な水分源なので、食事の後にも与える
月齢に応じた1日の目安量としては、生後6ヶ月〜1歳頃で母乳・ミルク以外に100〜200ml程度の水分補給が理想的です。マグやストローカップなど、赤ちゃんが使いやすい容器で提供しましょう。
赤ちゃんの便秘解消法③ 生活リズムを整える
便秘解消には食事や運動だけでなく、赤ちゃんの生活リズム全体を整えることも大切です。規則正しい生活習慣は腸の動きを活発にし、自然な排便を促します。
排便習慣をつけるコツ
赤ちゃんでも、少しずつ排便のリズムをつけることができます。以下のポイントを意識しましょう。
毎朝同じ時間に起こし、朝日を浴びることで体内時計が整い、腸の動きも活発になります。朝食(授乳や離乳食)後から30分程度は、便意を感じやすい時間帯です。この時間に排便のためのマッサージをすると効果的です。
また、排便のサインを見逃さないことも大切です。赤ちゃんが顔を赤くしたり、急に静かになったり、足をバタバタさせたりする様子は便意のサインかもしれません。そのタイミングでおむつを替えたり、便が出しづらそうであれば肛門刺激をすることで、排便を促せることがあります。
睡眠と便秘の関係
質の良い睡眠は自律神経のバランスを整え、腸の動きを活発にしてくれることが考えられます。赤ちゃんの睡眠リズムを整えるために以下のことを心がけましょう。
1. 毎日同じ時間に寝かしつけ、起こす習慣をつける
2. 日中は明るい環境で過ごし、夜は照明を暗めにする
3. 寝る前の強い刺激(明るい光、激しい遊び)を避ける
4. 寝かしつけのルーティーン(本の読み聞かせ、軽いマッサージなど)を決めておく
赤ちゃんの睡眠が安定すると、朝起きた後の排便も規則的になりやすくなります。特に生後6ヶ月以降は、夜にまとまって眠り、日中の活動時間をしっかり確保することで、体内リズムが整い、便秘の改善にもつながることが期待できます。
適度な運動と外出の効果
赤ちゃんの発達段階に合わせた適度な運動や外出は、腸の動きを活発にし、便秘解消に役立ちます。
発達段階別の運動例は以下になります。
・首がすわった頃:うつ伏せ時間を増やし、背中や腹筋を使う機会を作る
・寝返りができる頃:広いスペースで自由に動かせる環境を用意する
・お座りができる頃:体幹を使う遊びを取り入れる
・ハイハイの時期:十分に動き回れる安全な空間を確保する
・歩き始めの頃:外出して歩く機会を増やす
ただし、赤ちゃんに過度な運動や刺激を与えないよう、様子を見ながら適度に行うことが大切です。無理なく楽しく体を動かせる環境づくりを心がけましょう。
便秘が続く場合の対処法と医師への相談のタイミング
便秘を放っておくと便がますます硬くなり、さらに便秘が悪化する可能性があるため、自宅でのケアを続けても便秘が改善しない場合や、赤ちゃんの様子に気になる点がある場合は、専門家に相談することが大切です。ここでは、病院受診の判断基準や医療機関での対処法について解説します。
病院を受診すべきサイン
以下のようなサインがある場合は、小児科医への相談を検討しましょう。
- 5日以上排便がない
- 便が出ても極端に硬く、血が混じっている
- 激しく泣き続ける、機嫌が極端に悪い
- 嘔吐を伴う、食欲が極端に落ちている
- お腹が異常に張って硬い
- 水分をほとんど受け付けない(脱水のリスク)
特に脱水症状のサイン(尿の量が減る、唇が乾燥する、涙が出ない)がある場合は、早めに医療機関を受診することが重要です。また、新生児期(生後1ヶ月未満)の便秘は比較的まれなため、この時期の排便異常は便秘に見えて腹部の病気である可能性もあるため医師に相談しましょう。
まとめ
赤ちゃんの便秘は多くの親が直面する悩みですが、適切な知識と対策を知っておくことで、改善が期待できます。この記事でご紹介した対策を日常生活に取り入れてみましょう。
赤ちゃんのこうした成長のひとつひとつを見守る毎日が、子育てのやりがいであり、同時に忙しさでもあります。そんな子育て期の暮らしをもっと快適にするためには、住まいの工夫も大切です。アイフルホームでは、赤ちゃんや子どもの成長に寄り添った「キッズデザイン」の視点から、安全で片付けやすく、育児がしやすい住まいをご提案しています。毎日の育児がもっとスムーズに、家族みんなが笑顔になれる住まいづくりを考えてみませんか?