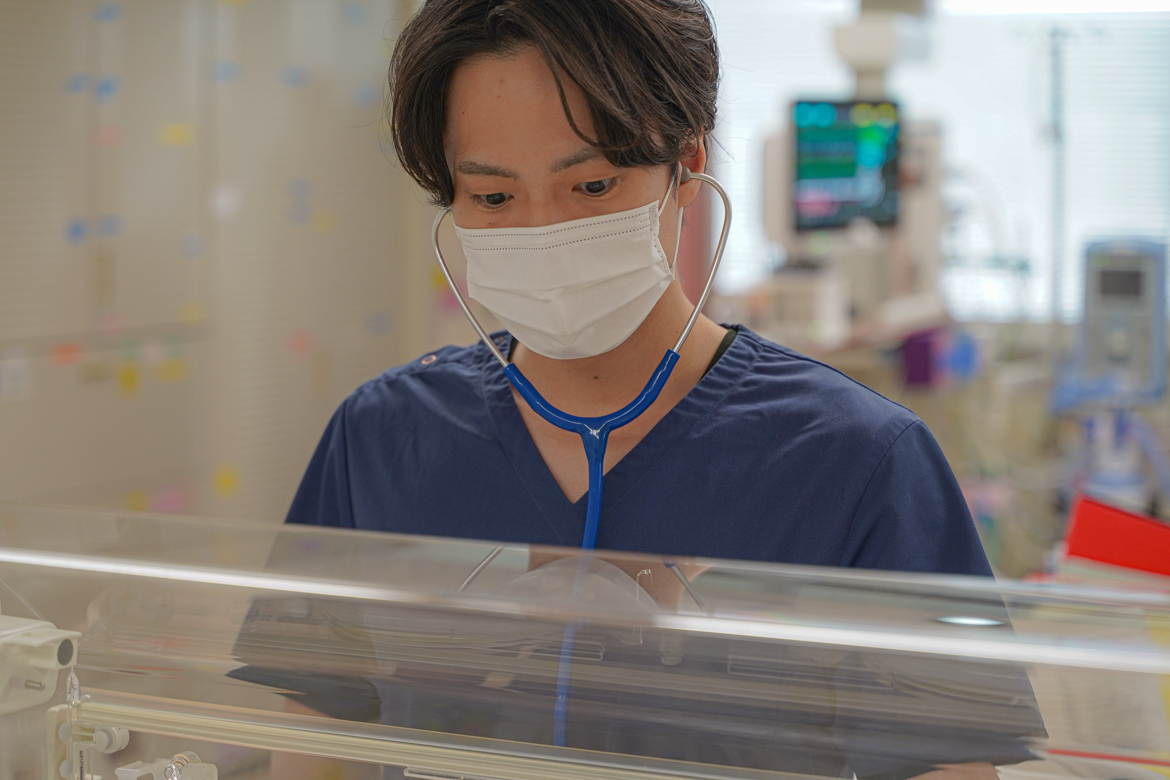母乳育児を続けたいけれど、「母乳の量、足りているのかな?」「赤ちゃんがお腹いっぱいになっていないのでは?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。母乳量に関する悩みは多くのママが経験するもので、決して一人だけの問題ではありません。
まず大前提として、母乳育児は非常に個人差があります。完全母乳育児が可能かどうかはライフスタイルや個人差などの問題がありどちらが正解かということはありません。とはいえ、少しでも母乳で育児をしたいというお声はよく聞きます。母乳量を増やすために、日常的に取り組めることはたくさんあります。今回は、小児科医監修のもと、母乳量が足りていない原因と増やすための方法、そして母乳育児を無理なく続けるためのコツをご紹介します。
母乳量が足りない?知っておきたいサインと原因
母乳育児を続ける上で、まず知っておきたいのは母乳量が十分かどうかだと思います。「母乳が足りていないかも…」という不安は、授乳の感覚だけでは判断しづらく、実際の母乳量と一致しないこともあります。正しい判断基準を知ることで、適切な対応ができるようになります。
母乳量不足のサイン
母乳量が足りているかどうかは、赤ちゃんの体重増加と排泄回数で判断するのが最も確実な方法です。赤ちゃんの体重が順調に増えていて、十分な量の尿が出ていれば、基本的に母乳は足りていると考えられます。新生児であれば、授乳のたびに排尿していることも珍しくありません。月齢とともに尿回数は減少する傾向がありますが、1日に6−8回程度、淡黄色の尿が出ていれば問題ありません。
一方で、赤ちゃんの体重増加が緩慢な場合(新生児期で日増25g以下)や、授乳後もすぐに泣いてしまう、授乳時間が極端に長い(1時間以上)、おしっこの回数が1日6回未満といった状態が見られるときは、母乳だけでは不足している可能性があります。
母乳量が減少する主な原因
母乳量の減少には複数の要因が関わっています。一つの要因としては授乳回数の不足で、赤ちゃんの吸啜刺激が少ないと母乳分泌を促すホルモンの分泌が減少してしまいます。
その他にも、ママの疲労やストレス、栄養不足、水分摂取不足、睡眠不足なども母乳量減少の原因となります。また、薬の服用や病気、月経の再開なども影響する場合があるため、気になる症状がある場合は医師に相談することをおすすめします。
過去に子育てと家事を両立するためのコツについても紹介してます。ぜひ、以下の記事も参考にしてみてください。
子育てと家事を無理なく両立!時間もココロも余裕が生まれる暮らしのコツ | Sodate(ソダテ)
母乳量を正しく判断する方法
母乳量を正確に測定するには、授乳前後の赤ちゃんの体重を測る方法があります。赤ちゃん用の体重計がなければ、大人が赤ちゃんを抱っこして得られた体重から、大人の体重を引けば大まかな赤ちゃんの体重がわかります。しかし、家庭で毎回測定するのは現実的ではありません。日常的には赤ちゃんの機嫌や眠りの質、排泄の状況を総合的に観察することが大切です。
母乳外来や助産師による定期的なチェックを受けることで、より正確な判断ができます。不安を感じたときは一人で悩まず、専門家に相談することで適切なアドバイスを得られるでしょう。
母乳量を増やす基本的な方法
母乳量を効果的に増やすために、赤ちゃんの自然な吸啜刺激は重要な要素であると言えます。吸啜刺激は母乳を作成、分泌を促すホルモン分泌を刺激する為、赤ちゃんがより多く、より効果的に吸うことで分泌量も自然に増加することが期待できます。また夜間は母乳の作成を促すホルモン値が高い傾向にあり、夜に授乳をすることでより母乳の量を増やすことができる可能性があります。
頻回授乳の実践
母乳量を増やすために最も効果的な方法は、1日8〜10回以上の頻回授乳です。赤ちゃんが欲しがるときにすぐに授乳することで、乳房への刺激が増え、母乳を作るプロラクチンと母乳を分泌するオキシトシンの分泌が促進されます。
新生児期は2〜3時間おきの授乳間隔になることが多いですが、授乳間隔にこだわりすぎず、赤ちゃんの欲求に合わせて柔軟に対応することが大切です。。時間を気にしすぎず、赤ちゃんの授乳のサインを見逃さないよう心がけましょう。
夜間授乳の重要性
夜間授乳は母乳量増加において特別な意味を持ちます。夜間はプロラクチンの分泌が最も活発になるため、この時間帯の授乳は母乳量増加に大きく貢献します。
夜間授乳を続けることで、日中の母乳分泌量も安定し、全体的な母乳量の底上げが期待できます。無理に夜にたくさん授乳をさせようとするのではなく、どうしても避けられない夜の授乳も、いいことがある、と思って実施するのがいいと思います。可能な範囲で夜間授乳を継続することをおすすめします。
正しい授乳姿勢と吸着
効果的な母乳分泌のためには、赤ちゃんが正しく乳房に吸着することが欠かせません。浅い吸着では十分な刺激が得られず、ママの乳頭痛の原因にもなります。赤ちゃんの口が大きく開いて、乳輪の大部分を含んで吸着している状態が理想的です。
授乳姿勢も重要なポイントです。ママがリラックスできる姿勢で、赤ちゃんの体全体がママの方を向いている状態にしましょう。横抱き、縦抱き、フットボール抱きなど、様々な姿勢を試して、お互いに楽な位置を見つけることが大切です。
母乳分泌を促進する生活習慣とセルフケア
母乳量を増やすためには、授乳以外の生活習慣も大きく影響します。ママの体調管理と心身のケアを通して、自然な母乳分泌をサポートすることができます。日常的に取り組める具体的な方法をご紹介します。
適切な栄養と水分摂取
母乳育児中は通常よりも500〜700kcal程度多くのエネルギーが必要になるため、バランスの良い食事を心がけることが重要です。
水分摂取については、十分にとるようにしましょう。過度に水分を摂取する必要ありませんが、こまめな水分補給は母乳の量を維持する上では必要なことです。授乳前後に水分を取る習慣をつけると、自然に適切な水分量を確保できます。
乳房マッサージとケア
乳房マッサージは母乳分泌促進に効果的なセルフケア方法です。入浴時や授乳前に、乳房基底部から乳頭に向かって優しくマッサージすることで、血流や、母乳の流れがスムーズになります。
ストレス管理とリラクゼーション
ストレスは母乳分泌に大きな影響を与えるため、リラクゼーションの時間を意識的に作ることが大切です。深呼吸やヨガ、好きな音楽を聴くなど、自分なりのリラックス方法を見つけましょう。
育児中は完璧を求めすぎず、家事や育児を家族と分担することで心理的な負担を軽減できます。十分な休息と睡眠を取ることも、ホルモンバランスを整え、母乳分泌をサポートします。
もし、寝かしつけにより睡眠不足になってしまっている方は、下記の記事も参考にしてみてください。
寝かしつけのコツ。2〜3歳の子供のなかなか寝てくれない時の対処法やコツ | Sodate(ソダテ)
また、リラックスできる「ベビーマッサージ」についても過去の記事で紹介しています。ぜひ、参考にしてみてください。
ベビーマッサージのやり方と効果とは?赤ちゃんと一緒にリラックス! | Sodate(ソダテ)
母乳量を増やすための実践テクニック
母乳量増加のためには、効果的なテクニックの実践も有効です。搾乳器の使用方法から、授乳を支援する様々なアイテムまで、実際に多くのママが効果を実感している方法をご紹介します。
搾乳器を活用した母乳量アップ
搾乳器を使った追加刺激は、特に母乳量が減少気味の時期に効果的な場合があります。授乳後に5〜10分程度搾乳することで、乳房への刺激が続き、次回の授乳に向けて母乳分泌が促進されることあります。
手動と電動の搾乳器がありますが、ご自身にあった方を選択して問題ありません。頻繁に使用する場合は電動タイプが、搾乳作業が自動なので便利かもしれません。搾乳した母乳は冷蔵保存し、次の授乳で足りない分を補うために使用できます。搾乳のタイミングは授乳後だけでなく、朝の分泌量が多い時間帯に行うのも効果的です。
授乳クッションと姿勢の改善
授乳クッションの使用は、正しい授乳姿勢を維持し、ママの負担を軽減するのに役立ちます。適切な高さに赤ちゃんを支えることで、深い吸着を促し、効率的な授乳の助けになります。
姿勢の改善により、乳管の圧迫を防ぎ、スムーズな母乳の流れを確保できます。長時間の授乳でもママが疲れにくくなるため、頻回授乳を続けやすくなるでしょう。
温罨法と冷罨法の使い分け
温罨法は授乳前に行うことで血流を促進し、母乳の分泌と流れを良くします。40〜45度程度の温かいタオルを乳房に5〜10分当てることで、射乳反射が起こりやすくなります。
一方、授乳後の冷罨法は乳房の腫れや痛みを軽減し、過度な分泌による乳腺炎の症状緩和につながります。タイミングを見極めて使い分けることで、より効果的な母乳ケアができます。
母乳が足りない場合のミルク補足と注意点
母乳量を増やす取り組みを行いながらも、赤ちゃんの成長に必要な栄養を確保するため、適切なミルク補足が必要になる場合があります。ミルク補足は母乳育児の失敗ではなく、赤ちゃんの健康を守るための大切な選択です。
適切なミルク補足のタイミングと量
ミルク補足のタイミングは、体重増加の状況や赤ちゃんの様子を総合的に判断して決定します。基本的には授乳後に赤ちゃんが満足していない様子を見せる場合や、体重増加が不十分な場合に検討します。
補足量は赤ちゃんの月齢と体重、授乳間隔などを考慮して調整しましょう。もしどのくらい足せばいいかわからない場合には、少なめに補足してみて、すぐに泣いてしまうなど足りなさそうな様子があれば、少しずつ補足量を増やすという方法がいいと思います。1人でどうしたら良いかわからない時には、保健師や助産師にも相談してみましょう。
混合栄養を成功させるポイント
混合栄養を行う場合は、母乳を優先してあげて、ミルクは補足として位置づけるといいと思います。。まず母乳をしっかりと飲ませ、足りない分をミルクで補うという基本原則を守ることで、安心して母乳分泌を維持しつつ赤ちゃんに十分な栄養を与えることが可能になります。
哺乳瓶の乳首選びも重要なポイントです。一部の赤ちゃんは授乳方法の違いで、直接母乳が進まなくなることがあります。赤ちゃんそれぞれにあったサイズや商品を選ぶことで母乳とミルク両方がうまく使う役にたつと思います。
母乳育児への影響を最小限に抑える方法
ミルク補足を行いながらも母乳育児を継続するためには、授乳回数を減らさないことが重要です。ミルクを与えた場合でも、次の授乳は予定通り母乳から始めることで、乳房への刺激を維持できます。
ミルクを与えている間も、搾乳器を活用して乳房への刺激を続けることで、母乳分泌量の維持と増加の役にたつことが期待できます。医師や助産師と相談しながら、個々の状況に合わせた最適な方法を見つけていきましょう。
専門家によるサポートを受ける方法
母乳育児の悩みは一人で抱え込まず、専門家のサポートを積極的に活用することが大切です。経験豊富な専門家からのアドバイスは、効率的な問題解決につながり、ママの不安軽減にも大きく貢献します。
母乳外来の活用
母乳外来では、助産師や看護師が個別の状況に合わせてきめ細かいサポートを行っています。実際の授乳場面を確認してもらうことで、姿勢や吸いつきの癖などもその場で調整してもらえます。
母乳量の測定や乳房の状態チェック、マッサージ指導なども受けられるため、ひとりでは不安なことも安心して相談できます。定期的に通うことで、授乳の経過を一緒に見ながら無理のない方法を提案してもらえるのも大きなメリットです。
助産師や保健師への相談
地域の助産師や保健師も、母乳育児の心強い存在です。家庭訪問サービスを利用すれば、いつもの環境で授乳指導を受けることができ、より現実的なアドバイスを得られます。
乳児健診の機会も、母乳に関する相談をする絶好のタイミングです。赤ちゃんの成長曲線と照らし合わせながら、母乳量の適切性を評価してもらえるため、客観的な判断基準を得られます。
まとめ
母乳量を増やすためには、赤ちゃんに繰り返し授乳することが肝要です。正しい授乳姿勢での効果的な吸啜刺激が母乳の維持、分泌を促します。同時に、バランスの取れた栄養摂取と十分な水分補給、適度な休息とストレス管理により、ママの体調を整えることももちろん大切です。
乳房マッサージや搾乳器の活用、温罨法などのセルフケアも母乳分泌促進にメリットがある場合があります。もし母乳だけでは不足する場合は、適切なミルク補足を行いながら母乳育児を継続する方法もあります。
一人で悩まず、母乳外来や助産師、保健師などの専門家のサポートを積極的に活用しながら、ママと赤ちゃんに最適な母乳育児のスタイルを見つけていきましょう。母乳育児は決して一人だけの努力で成り立つものではなく、周囲のサポートを得ることがとても大切です。
赤ちゃんのこうした成長のひとつひとつを見守る毎日が、子育てのやりがいであり、同時に忙しさでもあります。そんな子育て期の暮らしをもっと快適にするためには、住まいの工夫も大切です。アイフルホームでは、赤ちゃんや子どもの成長に寄り添った「キッズデザイン」の視点から、安全で片付けやすく、育児がしやすい住まいをご提案しています。毎日の育児がもっとスムーズに、家族みんなが笑顔になれる住まいづくりを考えてみませんか?